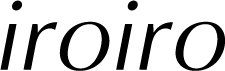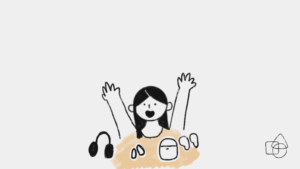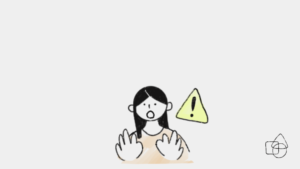本記事に出会ってくださりありがとうございます。
製作途中の内容を公開している状態です。年内にすべての記事を修正をかけ、完成させる予定です。
稚拙な記事状態ですが、少しでも困っている人の手助けになればと思い公開状態で修正しています。
今しばらくお待ちください。
皆さんは「聴覚過敏」だと知ったきっかけはありますか?
「聴覚過敏」だと知るきっかけは多くありますが、その中には親、学校の先生や医者など第3者や自分から気づくことや周囲の違和感を感じ、ネットで知ることが多いでしょう。
私の場合は少し特殊で、小学4年生頃に『光りとともに』という本に出会い「聴覚過敏」という存在を知りました。
母が私に「聴覚過敏かもしれない」と話した数ヶ月後、クリニックに行き「聴覚過敏」と診断を受けました。
今回の記事で伝えたい事としては音に我慢することや1人で抱え込むことが当たり前ではなく、クリニックに相談する事が大事だと気づきました。
周囲との聞こえ方の違いによる違和を持つように
私が「聴覚過敏」病院で診断された頃の当時は現在よりも浸透していなく、知っている人はADHD、ASDなどについて詳しいクリニックの先生や支援学級の先生しか知られてないことが多かったです。
勿論、私の場合は(車のクラクションや大きな声で叫ぶなど)大きな音や周りの音などが聞こえてしまいます。そのため、手で耳を塞ぐことが日常茶飯事でした。
家族は「時間が過ぎたら慣れてくるから大丈夫だよ。」と言われ、音や耳の痛みが相手に伝わえらない事がとても悲しく辛かったです。
「なぜ、そんなこと簡単に言うの。音を聞くだけでしんどくて辛いんだよ!私は。」と理解してくれないので、絶望していました。
時が過ぎるにつれ、苦手な音が増え、「何で耳を塞いでいるの?」や「耳を手で塞ぐのは変だよ」などと周囲の人達の冷たい意見や視線が心に傷つくこともありました。
(個人的に音が気になる)スーパーや保育園や小学校などの公共施設に行くと、すぐに手で耳を塞いで行動していましたが、周囲は手で耳を塞いでなかったことに衝撃を受けました。
家族や周囲がその行為をしてないことに気づき不思議に感じることが増え、周囲と私の聞こえ方が違うことにますます違和感を持つように感じるようになりました。
『光りと共に』と言う本と出会い
図書室で休憩時間を独りで過ごしていたある日、偶然手に取った本と出会った本が『光りとともに』です。
その本は自閉症や感覚敏感の向き合い方などをメインに書かれている漫画に出会い、初めて、「感覚過敏」や「聴覚過敏」という事を知ることや音や向き合い方について学びました。(*聴覚過敏だとまだ自覚してない)
もし、『光りともに』という本に出会えなかったら防音アイテムや音などの向き合い方が分からずに、困っていたと思います。
母が気づき、私に「聴覚過敏」と思うと話したことがきっかけで知るように
年齢が上がるに連れて、周囲の音や大きい音などが気になるようになった私は、外出やイベントに行きたいと言う事が少しずつ減りました。
その事がきっかけで、私が音で困っている事に母が気づき、ネットや支援学級の先生に相談した事で娘が「聴覚過敏」だと確信するようになったのです。
ある日、母が私に「あなたは聴覚過敏かも。」と話してくれました。最初は「聴覚過敏」の存在を知っていましたが、自分が持っている可能性がある事を思ってもいなかったです。母が「一旦、クリニックで診断を受けて、今後のことについて考えよう。」と母が言ってくれた事がきっかけでクリニックに行こうと決意しました。
クリニックで「聴覚過敏」と診断を受けた
私が10歳の秋頃、母と一緒にクリニックへ行き、問診や検査を行いましたが診断結果が「聴覚過敏」でした。
当時の検査や問診の内容は忘れてしまいましたが、覚えている事としては、先生が親身に寄り添って、1からわかりやすく教えてくれたことを覚えています。最初は診断された時は幼かったためよく分からなかったのですが時間が流れ、理解するようになりました。
母が「クリニックに行こう。」と提案してくれた事で、今まで音や周囲の違和感で悩んでいた理由を知れて、安心する事が出来ました。
また、「聴覚過敏」についての音に苦しませずに過ごす方法や向き合い方や生活改善の方法を教えてくれたことが、何よりも心強かったです。
音に我慢することや1人で抱え込むことが当たり前にならず、クリニックに相談することが大切です。
・検査しやすい耳鼻科の先生に診察する
・原因が特定できず診断が出ないようであれば、心療内科や精神科で検査を受けることをオススメします。