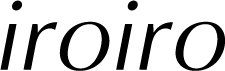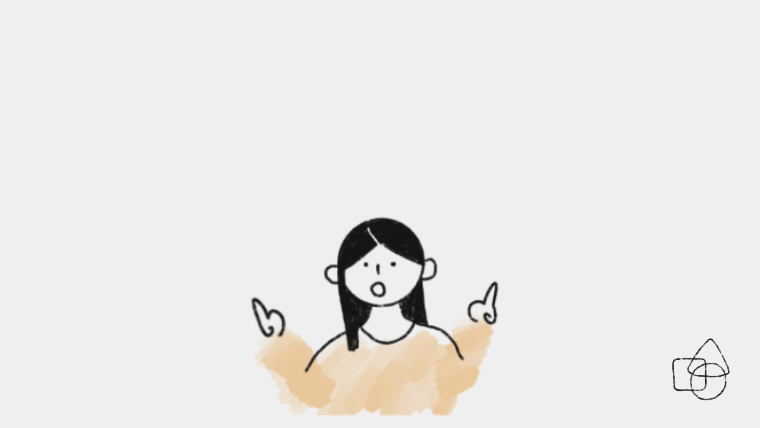本記事に出会ってくださりありがとうございます。
製作途中の内容を公開している状態です。年内にすべての記事を修正をかけ、完成させる予定です。
稚拙な記事状態ですが、少しでも困っている人の手助けになればと思い公開状態で修正しています。
今しばらくお待ちください。
音で困っている人の中には「聴覚過敏なのか?」「ミソフォニアなのか?」と症状名で迷う人は少なくないです。聴覚過敏をもつ私がミソフォニアも併存してから数年経った今、思うことをまとめてみました。
聴覚過敏をもっている人はミソフォニアも併存しやすい
「聴覚過敏」を持っている人は「ミソフォニア」になりやすいと考えられています。
「聴覚過敏」は文字通り、聴覚に過敏な耳を持っているため、音に対して感度が高く、大小関係なくいろんな音を拾いやすいです。
「聞こえすぎる」=「嫌な音が不快感につながる」人にとっては、ストレスを感じるより音に対する過敏度が上がることがあります。
ストレスや環境 がトリガーとなり、「ミソフォニア」の特徴でもある、「人が出す音」や「特定した音」が嫌悪や怒りに感じるようになると捉えています。
聴覚過敏以外にもミソフォニアになりやすい人の特徴に、
- HSP(=繊細な人)
- 自律神経が乱れている状態
- 生理中
HSP(=繊細な人)な人や、自律神経が乱れている場合も聴覚過敏を持つ人と同様に「ストレス or 環境」「またはふとした瞬間や気づかない間にその音がトリガー(苦手の音)となり」ミソフォニアになりやすいと考えています。
聴覚過敏だけじゃなくミソフォニアかもと思った出来事〜私の場合
私が10歳の頃に「聴覚過敏」と診断されました。
診断前は環境で作られた大きい音(マイク、機械類など)や高音(超音波など)が苦手で、その環境にいることが苦痛で、音に怯える日々を送っていました。
「聴覚過敏」診断後、防音アイテムを着用するようになりました。
思春期によるストレス(人間関係や音)により高校1年生になると人が出す音(パソコンのタイピングの音、シャーペンのカチカチ音、咀嚼音など)や特定の音に対して、神経質になり、日常生活が苦痛に感じるようになりました。
そのことがきっかけで知っている「聴覚過敏」の情報とは違うように感じはじめ、ネットで調べた結果、「ミソフォニア」という言葉を知りました。環境の変化や音に対するストレスが高くなったことで、ミソフォニアも併存したのだと今は思っています。
聴覚過敏とミソフォニアの違いや分け方
「聴覚過敏」と「ミソフォニア」はほとんど似ているため、分かりづらいのが事実です。
聴覚過敏とミソフォニアの違いと見分けるポイントは主に2つです。
- 耳から入ってくる音の聞こえ方
- 音に対する嫌悪感や憎しみがあるかないか
聴覚過敏は「(音量の大小に関係なく)すべての音を拾ってしまう。音が大きく響くように聞こえる。」または「一つ一つの音を聞き分けることが難しく、すべての音が同じボリュームで聞こえてしまう。」ことが特徴です。
周囲の人にとって何気ない音が、聴覚過敏の当事者によっては騒がしく聞こえ、苦痛に感じてしまう事もあります。音に対してミソフォニアが持っている特有の音への憎しみや殺意はなく、「騒音をなんとか回避したい」、「静かにしてほしい」と思っている人がほとんどです。
ミソフォニアは「周囲の音よりも(大小関係なく苦手やトラウマだと感じる)特定した音に対して音が大きく聞こえる。」、「周囲の音にはあまり気にならない」のが特徴です。咀嚼音、タイピング音の他、人が作業する時の音や電子音など個人的に苦手な音が聞こえると、憎悪やイライラ、苦手意識が強く感じる事があり、殺意が強くなります。
もし、聴覚過敏とミソフォニアの違いと見分ける特徴が違う場合は聴覚過敏とミソフォニアを併合している可能性が高いです。
聴覚過敏の研究は1940年代からはじまり、ミソフォニアの反応も含まれていました。2010年代以降、聴覚過敏とミソフォニアを症状名に区分し、ミソフォニアの研究が開始されました。
最後に、ミソフォニアで困っている人へ
診断方法が定まっていないことことから医療に頼ることも難しく、ミソフォニアの認知度は低いことから生活しづらい点もあるのが現状です。
診断書について
診断書がなくては学校で配慮を受けることは難しく困っている方も多いと思います。ミソフォニアは自律神経に関連することやまた聴覚過敏の中に含まれていたことも踏まえ、聴覚過敏の診断やまたは別名の症状名で診断書をいただくのが現段階の方法だとしてはベターかもしれません。
対策について
専門的対策ではないですが、私が思うポイントは「周囲に共有」することで少しでもストレスを減らし生活する方法でした。相手に伝える際は、イメージしやすくするため「黒板のひっかき音」を例に話したうえで、自分の苦手な音や感じ方防音アイテムを着けている旨などを説明し、理解・協力してもらえるようにしています。